こんにちは。
障害当事者(右麻痺・高次脳機能障害・てんかん等)で元・作業療法士のさやかです。
今回は注意機能と私の注意の後遺症について。
高次脳機能障害の一つである注意障害。
私はDr.から【行政的な高次脳機能障害】の診断は下りていません。
(そのため、精神障害者保健福祉手帳は所持していません)
ですが【学術的な高次脳機能障害】の後遺症があります。
行政的な高次脳機能障害についてはこちらをどうぞ。↓↓↓
行政的な診断は下りていなくとも、
後遺症として、「あれ?注意障害かな??」となっている事実があります。
◎デュアルタスクができない(歩きながら会話する、会話しながら食事する等)
◎一つの動作にのめり込む(作業をしているときに周りの声は聞こえない)
◎注意散漫(周りの情報を全て拾ってしまう)
◎うっかりミス多発
◎選択・決定に時間がかかる
(デュアルタスクについては後述します)
「私だってうっかりミスはあるよ〜〜!」と軽く捉えられてしまうことがあるのですが、
うっかりミスの数、異常な多さであったと思います。
5つの注意機能について
私の注意障害と思われるものについて触れる前に、
注意機能について簡単に書いていきたいと思います。
「注意障害」と言われると、「注意機能が低下している」という風に思われるかもしれません。
低下もありますし、亢進(物事の度合いが激しくなること)する場合もあります。
亢進と低下をバランス良く必要なときに使えなくなるのが注意障害かな、と。
(※注意の低下・亢進は、思考の連続性や切り替えに絶対に必要なものです)
選択性
持続性
転導性
多方向性
感度
神経心理学入門(山鳥重)より出典
ネットで検索すると「選択性・持続性・転導性・多方向性」の4つとされていたり、
上記の4つに抑制性を加えたものもありましたが、今回の記事では「神経心理学入門」にそって、書いていきたいと思います。
各々、説明していきますが、軽〜〜〜く流してください。
選択性
必要な情報に注意を向ける機能。
持続性
選択した情報に注意を持続させる機能。
転導性
注意をきりかえる機能。
多方向性
同時に多方向に気を配る機能。
(この機能があるから注意の転導が可能になる)
感度
感度は注意力そのもの。
感度があるからこそ、注意を選択したり持続させたり切り替えることができる。
その感度が低下してしまうと無関心・ぼぉ〜〜としてしまう。
感度があってこそ、その他4機能が活きてくる。
私の注意の後遺症
①デュアルタスクができない
デュアルタスク(二重課題)とは、身体を動かす作業と、思考を伴う作業を組み合わせるタスク。
とても苦手な行為です。
病気になってみて、健常の方たちがすいすいとデュアルタスクをこなしている姿を見て、悔しい通り越して打ちひしがれました。
(自分から行動をおこしていないくせに)
マルチタスクという似たような言葉もありますが、
こちらは【複数の思考を伴う作業を同時に行う(ように見えて短時間で切り替える)タスク】であり、人間の脳のパフォーマンスが低下するとされています。
マルチタスクはね。
全人類が苦手だと思う。
できなくて良いと思う。
ここでは、
【マルチタスク】と【デュアルタスク】は違うものとして書きます。
◎歩きながら話す
◎話しながらの食事
◎メモをとる
などなど
基本的に運動を伴うなら運動だけ。
話すときは座って。
体を少しでも動かすのであれば、思考活動は停滞します。
特に就労復帰したときに、「メモをとる」の部分で苦労した記憶があります。
①話を聞く(聴覚理解の低下があるので最初の関門!)
②頭の中で話をまとめる(聴覚理解の低下・注意の持続性の低下で内容が飛んでる)
③筆記するor打ち込む(そもそも話が飛んでいるのでここで強制終了!)
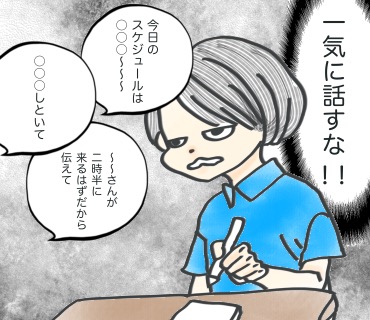
それを同時!!!!!!!
無理だった!!!!!!!
電話応対なんて遥か高みの作業です。
デュアルタスクに対する対策はしていますが、この場で書いていくとかなりの文字数になるので、別記事にあげます。
②ひとつのことにのめり込む
持続性が異様に亢進して、転導性・多方向性が低下しているパターンです。
一度このパターンに入ると、人に声をかけられても絶っっ対に気付きません。
この集中力が勉強中に発動すればっっ・・・!!!と、何度も悔しく思っています。
この部分については、特に対策は設けていません。
理由としては、大きな刺激(大きな声・触覚刺激)であれば気付くから。
あえて対策を一つ挙げるとするならば、職場への根回しという連携です。
③注意散漫・うっかりミス多発
今度は、持続性が低下して、多方向性が亢進した結果、転導性が亢進しているパターンです。
私の場合、記憶障害はないですが(たぶん)、上記のパターンでよく記憶が飛びます。
注意の持続性がないもんで、「あれ?私はいま何をしようとしてた?」と・・・。
(あれ?もしかしたら認知症?)
これっがとっっっても回数が多いのですよ・・・!
ワーキングメモリーの話にもなるのですが、WMの話は別記事で。
④選択・決定することに時間がかかる
選択性・持続性の低下、多方向性・転導性が亢進している、複合的なパターンだと思います。
選択・決定することに時間を要する具体的な場面は、私の場合は買い物かと思います。
スーパーに行ったら、自分が何をするのか・何を選んでいいのか、分からなくなってしまう。
いや買い物するんでしょ、と自分で突っ込む侘しさを毎度感じていました。
私の場合、「選ぶ対象が多すぎるのがいけないのでは??」と思っています。
スーパーのような大きな店舗で、いろんなものが視界にはいってくる。
選択性の低下により、周りの刺激を全て自分の中に取り込んじゃう。
そりゃ気ぃ散る。
いざ現場に立つと、全ての刺激を回収して転導するというループを繰り返し、
自分のワーキングメモリーを無駄に消費してしまう。
というわけで、刺激の少ないorコントロールできる自宅などで、買い物をする前に買うものリストを作る。
買うもの以外のコーナーには行かない。
よく購入するものに関しては、定番としてそれしか買わない。
(牛乳・卵は一番安いの、ヨーグルトはBifix砂糖なし、お菓子はきのこの山)
浮気はしない!!!
という、ありきたりな対策です。
でも有効。
頭のホワイトボードを照らす光
ワーキングメモリーは【頭のホワイトボード】とも言われています。
作業する際に、ちょっと頭に留めておきたい。用が終わったら、さっと消す。
作業する机やボードの光の状況によって、狭くなったり広くなったりします。
光が弱いと狭く、光が全体を照らしていると、本来のスペースをひろびろと使える。
その光は注意機能。
その注意機能も、体調や精神の状態、環境によって変動する。
体調が悪い時、メンタル落ち込んでいるときは、無理しない!
何もしない!!ゆっくりする!!!!
ちょっと回復してきたら、環境を少しずつ少しずつ、アップデートしていく。
それぐらいが丁度よいです。
では。
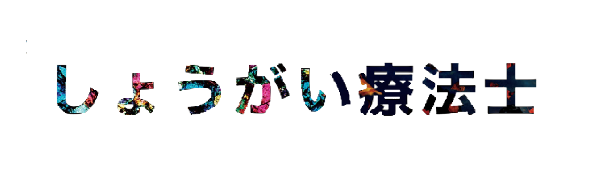
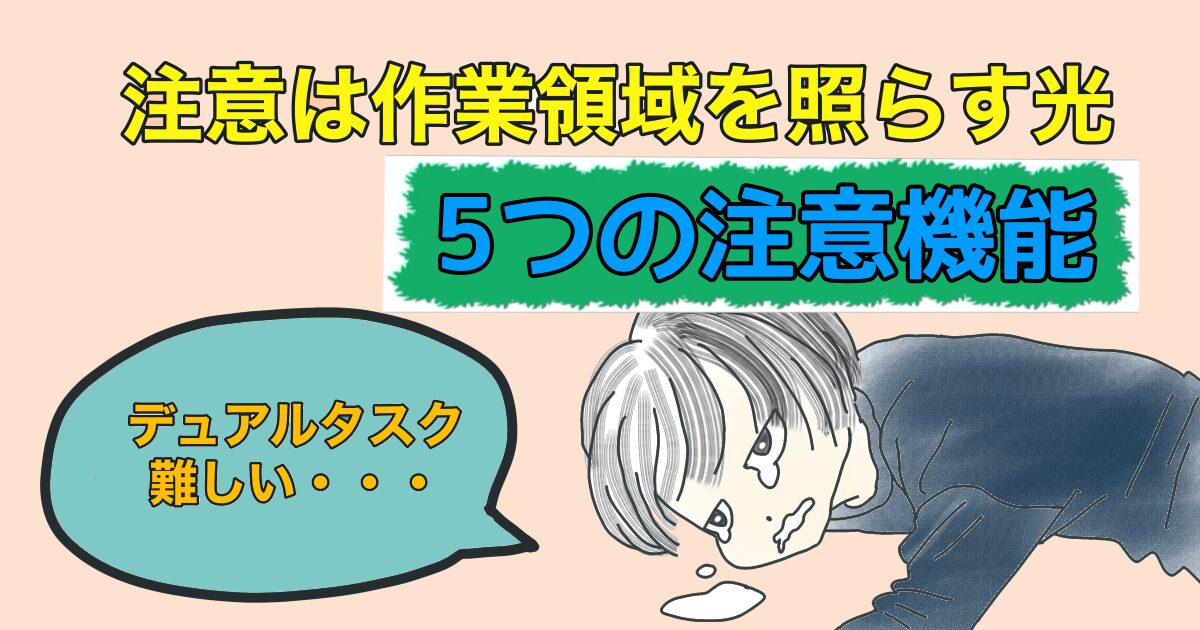


コメント